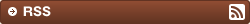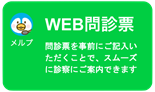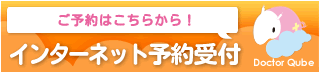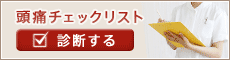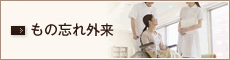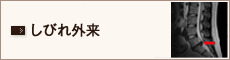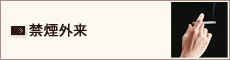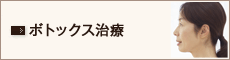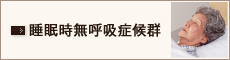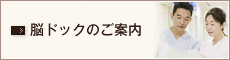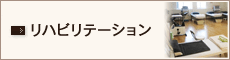脳卒中予防と食事
2019年06月08日
脳卒中を予防するためには「減塩」が推奨されています。
1日の食塩摂取量は6g以下が目標です。
動脈硬化予防目的で、野菜、果物の摂取、低脂肪食、魚類、、大豆、海藻、きのこ、未精製穀類の摂取が推奨されています。
また食事はカロリーオーバーに注意が必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
認知症と頭部MRI検査
2019年06月01日
認知機能低下の原因として「脳小血管病」があります。
頭部MRI検査で、無症候性脳梗塞、大脳白質病変、脳微小出血がみられることがあります。
血管性認知症の原因として最も多いのが、脳小血管性認知症です。
頭部MRI検査でこのような所見がある場合は、認知機能の詳しい検査が必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
頭痛と脳腫瘍
2019年05月25日
頭痛もちではない人が、最近になり頭が重いなどの症状が持続する場合は脳腫瘍などの可能性もあります。
脳腫瘍にも良性のものから、悪性のものまでさまざまあります。
良性の脳腫瘍であるとまずは手術が検討されます。
悪性の脳腫瘍は放射線治療や化学療法が必要になってくる場合もあります。
普段ない頭痛が継続する場合は病院で相談しましょう。
こくぶ脳外科・内科クリニック
夜はちみつダイエット
2019年05月14日
最近出版された「ダイエット」に関する書籍です。
ダイエットを考えている人に参考になる情報が書かれており、お勧めです。
こくぶ脳外科・内科クリニック
頭を打撲したあとの脳出血
2019年05月11日
頭部を打撲したあと、約1か月かけて脳出血を起こすことがあります。
これを慢性硬膜下出血といいます。
頭を打った直後は問題なくても、しばらくしてから血液が脳にたまってきます。
高齢者の方に多く、軽い打撲でも起こることがあります。
出血が脳を圧迫する場合は手術が必要になる場合もあります。
こくぶ脳外科・内科クリニック
突然の頭痛とくも膜下出血
2019年04月20日
今まで頭痛のなかった人が突然頭痛を起こした時は、くも膜下出血の可能性もあります。
くも膜下出血は脳の血管に脳動脈瘤ができてそれが破裂することで発症します。
治療としては破裂した動脈瘤に対してクリップをかけるかカテーテルで動脈瘤をふさぐ方法があります。
頭のMRI・MRA検査をすることによって出血する前の脳動脈瘤を見つけることもできます。
今までにない頭痛が起こった場合は早めに病院に受診してください。
こくぶ脳外科・内科クリニック
高齢者のフレイルと認知症
2019年04月13日
高齢になると筋力が低下し運動機能も低下します、また精神面でも衰えて虚弱になります。
このような状態が続くと認知機能の低下が進んでしまいます。
栄養不良、体重減少が認知機能低下の原因なると言われています。
また認知症が進むと心身の虚弱になっていきます。
認知症予防のため虚弱にならないように栄養や運動の管理が大切になっていきます。
こくぶ脳外科・内科クリニック
頭痛で生活に支障をきたす
2019年04月06日
頭痛にはさまざまな原因がありますが、ひどい場合は日常生活に支障をきたし学校や仕事に行けないこともあります。
また頭痛が原因で頻回に市販の頭痛薬が必要な方も多いです。
原因の一つに片頭痛があります。
片頭痛は、脈打つ痛みで吐き気があり、光や音に過敏になるのが特徴です。
片頭痛に効く薬が病院で処方可能ですのでご相談ください。
こくぶ脳外科・内科クリニック
こくぶ脳外科デイケアセンターのすすめ
2019年03月25日
こくぶ脳外科では通所リハビリ(デイケア)を行っております。
当院での特徴は、筋トレを中心に行うことと約1時間の短時間であることです。
高齢になり物忘れが進み、膝や腰に痛みがでてきますが、運動不足(筋力不足)が悪化要因になっていることが多いようです。
リハビリを行って改善したら近所の通所介護を利用して頂くことになる場合もあります。
介護保険が必要になりますのでケアマネージャーさん等とご相談下さい。
こくぶ脳外科・内科クリニック
尿酸値が高いとどうなるか?
2019年03月16日
尿酸が高いと関節にたまって痛風発作などを起こすことは有名です。
それ以外にも、高尿酸血症は高血圧や糖尿病などの生活習慣病や慢性腎臓病を合併しやすいと言われています。
尿酸が高いとこれらの疾患と関連して動脈硬化を進めていきます。
その結果脳梗塞や心筋梗塞を起こすことがあります。
尿酸を適切な値に保つことが大切です。
こくぶ脳外科・内科クリニック